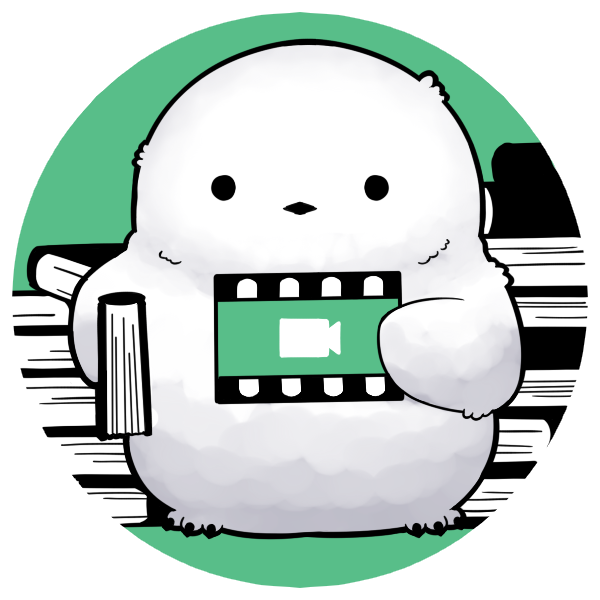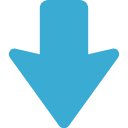【テレビ朝日】 2021.04.14 12:46
2021.04.14 12:46
警察官もユーチューバーに コロナ下の交通事故減へ
「シーン6、スタート!」。威勢のいい掛け声とともにカメラが回る。3月の昼下がり、東京・荒川区にある公園で数人がYouTubeで配信するための動画を撮影していた。自転車の女性「あなたが横断歩道じゃないところをいきなり渡ってきたからぶつかっちゃったじゃないの」高齢の歩行者「ここを渡るのがスーパーに行くのに一番近いんじゃい」2人が演じているのは、実際に起きた自転車と歩行者の交通事故の模様。倒れた自転車の前で運転手と高齢の女性が口論になった様子を再現している。実は、この撮影をしているのも演じているのも警察官、警視庁・尾久署の交通課員だ。手作り感満載のカンペが慌ただしく捲られ、セリフはどこかぎこちない…。最終的に、駆け付けた警察官が双方の話を聞いて事故処理をし、自転車事故の危険性を訴えるというシーンで撮影は終了した。この日撮影された動画はその後、やはり警察官らの手によって編集され、YouTubeチャンネルで3月30日に公開された。動画では、自転車のハンドルに荷物をかけると危険だという普遍的なことだけでなく、歩行者の表情がマスクでわかりにくいことから運転手に横断の意思を伝える行動が事故防止につながるという、今だからこその問題などが訴えられている。尾久警察署がこのような取り組みをするのには2つの理由がある。■都内の交通事故の死者数が全国ワースト1位に! 安全教室は減少…新型コロナウイルスの影響で、外出自粛が呼びかけられた去年、都内で起きた交通事故の数は減少したものの、死者数は155人となった。これは全国で最も多い数字で、東京都が死亡事故ワースト1位となるのは1967年以来のことだった。コロナ禍で交通量が減り車の走行する速度があがった事や、通勤手段をバイクなどにする人が増えたことが理由とみられている。警視庁・尾久署が管轄する荒川区では交通事故の約6割が自転車によるもので、今年に入り死亡事故も発生した。 一方で、地域の住民や子どもたちを集めて交通安全を訴える教室やイベントは、新型コロナウイルス感染防止の観点から軒並み中止にせざるをえない状況。尾久署でもおととし約350回行っていた交通安全教室の数が去年は150回以上減ったという。■『非接触型』がwithコロナの新しい交通安全教室そこで、尾久署の署員が目をつけたのがYouTubeチャンネルでの配信だった。地域住民が密にならずに交通安全を訴えるために、事故を再現した動画を撮影し、それを見てもらうという取り組みだ。尾久署の谷口正行(たにぐち まさゆき)署長は、「SNSの時代で、若い方だけでなく高齢の方もメディアを活用する生活様式になってきている。そこに着目した」と話す。YouTubeを使った行政機関による広報活動は近年、広がりを見せている。農林水産省公式YouTubeチャンネルの「BUZZ MAFF」は農林水産省職員自らがYouTuberとなり、農林水産物の良さや農林水産業、農山漁村の魅力を発信するプロジェクトで、今年4月時点で約2万3000人の登録者数となっている。担当業務にとらわれず、職員のスキルや個性を活かして農産物をPRする様子は話題となっている。また、それぞれの地域の特徴を活かした動画をYouTubeにアップして、各地の魅力をPRするという取り組みは、すでに多くの自治体の広報セクションで実施されている。警視庁も公式YouTubeにおいて、これまで詐欺被害への警戒や警察活動をPRする動画を配信してきたが、実際の犯罪抑止や交通事故防止などにいかに反映させていくかは、まだ課題が残されているという。警視庁は今年の重点目標の一つとして、コロナ禍における「新しい生活様式」の中でより有効な広報・啓発活動を掲げ、高齢者など相手の特性に応じて必要な情報が届くようにしたいとしている。この情勢で地域を守る警察官と住民が接点をもちにくい中、巷ではこの1年で様々な場面で「リモート」が浸透したように、警察活動においても、YouTubeを始め、あらゆるツールの利用を模索することが求められていくのだろう。谷口署長は「withコロナの交通安全教育として配信の動画を広くご覧いただき、交通安全の意識、事故防止に努めてほしい」と呼び掛けた。社会部 警視庁担当 松本拓也